こんにちは、みけ猫です。
実は私、つい先日「骨伝導イヤホン」を購入しました。
なぜ普通のイヤホンではなく骨伝導イヤホンを選んだのか?
理由や経緯を少しご紹介させていただきますね。

ワイヤレスって便利!
骨伝導イヤホンのご説明の前に、最近ではスマホなどの音源とコードをつながなくても音声を聴ける「ワイヤレスイヤホン」が多く見られますよね。
電化製品の売り場だけではなく、最近は100円ショップや、ゲームセンターの景品としても見かけることもあります。
多くの人がスマホを手放せない現代、スマホからコードをつながずに音声を聴けるのはとても助かりますよね。
コードでつないでいるイヤホンの方が音質が良いなど、好みの違いはあるでしょうが、イヤホンのコードが絡まったりしないので、私はワイヤレスイヤホンの方をよく使います。
私の場合はゲームの音声を聴くことが主な利用方法ですが、イヤホンをしていると着信音などにも気付きやすくなります。
電話のように長い着信なら振動や音でわかるのですが、メールやLINEなどの短い着信音は聞き逃しがちなので、とても助かっています。

骨伝導イヤホンとは?
イヤホンは通常、先端部分を耳に入れて使いますよね。
これはワイヤレスでもコードがあっても変わらないと思います。
では、骨伝導イヤホンとはどう違うのでしょう?
骨伝導イヤホンのしくみ
通常のイヤホンは、耳に入れた先端部分から音が出るので、その音を聞き取ります。
それに対して骨伝導イヤホンは、耳に本体を入れることはありません。
「骨伝導」の名前が付いているように、骨伝導イヤホンは頭部の骨に振動を送ることで、音声を聞き取ることができます。
骨伝導イヤホンの形
通常のイヤホンの場合、先端部分を耳に入れるので、基本的に小さな形をしていますよね。
対する骨伝導イヤホンは骨に触れて振動を送らないといけないので、耳に引っ掛けられるよう、独特な形をしています。
簡単に言えばひらがなの「つ」、マニアックに言えばヘ音記号や勾玉、といったところでしょうか。

しかしこれは片耳用のデザインなので、両耳で聞くタイプの骨伝導イヤホンはまた違った形になっているものもあります。
骨伝導イヤホンのメリット
骨伝導イヤホンは耳をふさぐことなく使えるので、周りの音も同時に聞こえるのが一番の特徴です。
これにより、周りの音が聞こえなくて起こるトラブルや事故の防止になります。
私が骨伝導イヤホンを選んだのは周りの音を遮らないことも理由の一つですが、それに加えて耳へのダメージを減らしたいのも理由の一つです。
私はアレルギー性鼻炎を持っていて、耳が痒くなったりすることがあるんです。
痒みってすごく辛いですよね。痛いのも辛いですが、痛みならある程度は我慢できるんです。
ですが痒みはどうしても我慢できず、イヤホンから耳に来る音の振動で耳が痒くなり、イヤホンが使えなくなる時があったりします。
私の場合、その対策として、直接耳に触れることのない骨伝導イヤホンを選んだのです。
メリットばかりじゃないけれど・・・
骨伝導イヤホンで、耳の負担は減らすことが出来ました。
ですがやはり骨伝導イヤホンは、通常のイヤホンよりやや聞こえにくい感覚はあります。
また、眼鏡を使っていると、マスクが必須の今は眼鏡、マスク、イヤホンの3重になり、落ちやすくなってしまうことも。
骨伝導イヤホンに限らず、ワイヤレスイヤホンはコード付きのイヤホンより落ちることは多いと思います。
コードがスマホなどとつながっているなら、耳から外れても下に落ちることはありません。まるでイヤホンの命綱のようですね。
とはいえ、落としたくないならばワイヤレスイヤホンも骨伝導イヤホンも、両耳同士がコードでつながっているタイプを選んだりすれば、落下は防げると思います。
骨伝導イヤホンの両耳同士がコードなどでつながっているタイプのものは作りがしっかりしていて落ちにくく、ランニングなどスポーツをするときでも活躍してくれます。
また、片耳用でもイヤホン自体に紐をつけるなど対策は出来ますし、使い方次第なのだと思います。
まとめ
以上が、私が骨伝導イヤホンを選んだ理由です。
ちなみに、私が買った骨伝導イヤホンは安めの物なのですが、最新の骨伝導イヤホンは全く違った形をしています。
どちらかと言うとワイヤレスイヤホンに近くてサイズも小さいので、耳にかけるタイプよりは落ちにくい構造なのかもしれません。
私が骨伝導イヤホンを選んだのは耳を刺激しないためでしたが、同じように「耳」に関して悩みを持つ人への参考になればと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!














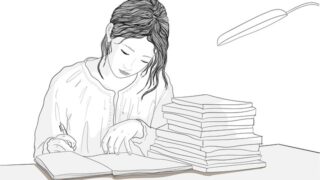






コメント